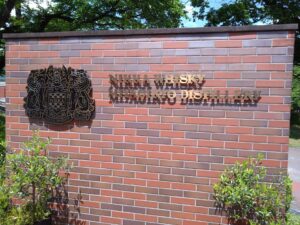日本のクラフト蒸留所訪問記 広島編


HP:SAKURAO DISTILLERY | 広島が世界に贈る、蒸留所
広島駅から広電で西へ約18分、長閑な風景に紛れた廿日市駅からほど近いところに桜尾蒸留所はあります。
桜尾蒸留所の全身は中国醸造株式会社とのことで、創業は大正7年、清酒や焼酎等の総合酒類メーカーだったそうです。
若くして五代目を継いだ現社長は社名をサクラオブリュワリーアンドディスティラリーに変えウイスキー、ジンの製造にチャレンジして現在に至るようです。

ベンチャー蒸留所とは違いある程度、酒作りの地盤があってのウイスキーやジン事業への方向転換や新規参入はよく聞く形です。
しかしながら、そう簡単にはいかないようで、こちらの五代目も設備投資、製造のノウハウ、販売のための営業等、苦労されたようです。
やはりウイスキーそしてジン、同じ酒と言っても焼酎や日本酒とは全く違うようですね。

見学コースをガイドさんの説明を聞きながら回って行くと、この新規事業への五代目の慎重さからか、
リスクマネジメントをしながらそして保険をかけながら更に個性的な商品を目指していた節、その痕跡が見えます。
特にジン作りに関して印象的だった事は地元広島のボタニカルにかなりこだわっていることでした。

歴史ある酒蔵となれば地元の名士。その五代目と聞けば俗に言う「ボンボン」かと思う人もいるかもしれません。
そのボンボンが流行りのジンやウイスキーを思いつきで作ったのか?
大変失礼ながらかく言う私も少なからず思ってました。
日本の酒事情を見てみると残念ながら日本人の日本酒や焼酎の消費量は減る一方です。
海外向けや外国人に人気で手に入らない銘柄を耳にする事はありますが、それはごくわずかなものです。
かつて日本の酒蔵を支えていたのは、労働を終えて大衆酒場に集まる庶民、晩酌という今でいう家飲みをするおっちゃん達でした。
現代人の傾向を見てみると和食店でもワインやウイスキー(ハイボール)を合わせる事が当たり前になり、
家飲みでもおつまみは洋食系が手軽かつ見栄えが良いようで、やはりワインや洋酒を合わせるようです。
残念ながら日本中の歴史ある酒蔵のほとんどは商品の見直しや事業転換を模索せざるを得ないという状況が現実のようです。
そんな事を言っている私も洋酒バーをやっております。
五代目のチャレンジは本音のところ追い詰められての苦肉の策か?そんな想像もしてみました。
これまでの日本酒、焼酎製造も引き続いており、ボタニカルはじめ地元密着で酒作りに取り組んでいるとのことです。
五代目と直接お会いすることはかないませんでしたが、今後も追いかけて行きたい蒸留所となりました。